
営業時間 9:00〜18:00
ご予約はこちら

営業時間 9:00〜18:00
ご予約はこちら

2025.09.11
近年、「朝起きても疲れが取れない」「ぐっすり眠れない」といった悩みを抱える人が増えています。仕事や家事のパフォーマンスを上げるには、質の良い睡眠が欠かせません。しかし、どうすればぐっすり眠り、スッキリ目覚められるか分からない方も多いのではないでしょうか。
そこで本記事では、睡眠の質を高める16の方法をわかりやすく紹介します。睡眠環境の見直しや生活習慣の改善に取り組むことで、翌朝スッキリ目覚める体づくりが可能です。今日から実践できるヒントを専門的な視点でお届けするので、眠りで困っている方は参考になるため、してみてください。
クマの原因が睡眠である方もいます。クマの種類や原因については、以下の動画で詳しく解説しているので、併せてご覧ください。
目元のクマに悩んでいる方は、ぜひKuma CLIへご相談ください。

良質な睡眠とは、短時間でも疲労をしっかり回復できる深い睡眠を指します。特に重要なのは、以下の3つの要素です。
睡眠の質を改善することで、体だけでなく脳の疲労回復にも効果があります。思考を司る脳は、良質な睡眠をとることで蓄積した目に見えない疲労の回復が可能です。脳の疲労が回復することで、健康の維持や成長の促進といった体の作用の改善が期待できます。
良い睡眠には、体内時計を整える規則正しい生活や、寝室の温度・明るさの最適化も欠かせません。快眠を得るための土台を知ることが、改善への第一歩です。

睡眠の質を妨げる要因は、多岐にわたります。特に影響が大きいのは、以下の3つです。
ここからは、それぞれの原因を詳しく解説します。
室温や湿度、光や騒音など、睡眠環境の乱れは質の低下に直結します。夏の寝苦しさや乾燥しすぎた空間では、深い眠りに入りにくくなります。また、LED照明やスマートフォンのブルーライトもメラトニンの分泌を抑制し、入眠を妨げる要因です。
騒音や振動も交感神経を刺激し、眠りを浅くする原因となります。こうしたことから、防音・遮光カーテンの導入や加湿器・空気清浄機の活用など、睡眠環境を整えることが重要です。
ストレスも睡眠の質を下げる大きな原因の1つです。仕事のプレッシャーや人間関係の悩みなど、現代人の多くが日常的にストレスを抱えています。ストレスは交感神経を優位にし、寝つきを悪くしたり中途覚醒を引き起こしたりすることも珍しくありません。
また、ストレスホルモンであるコルチゾールが増加すると、睡眠の深さにも影響を及ぼします。入浴やストレッチ、瞑想などで副交感神経を優位にする習慣を持つことで、心身のリラックスと深い眠りにつながります。
睡眠の質は日中の行動にも左右されます。夜遅くまでの飲酒やカフェイン摂取、スマートフォンの使用は、睡眠リズムを大きく乱します。また、運動不足や不規則な食事も、体内時計を狂わせる要因です。
寝る直前の飲食は胃腸を活発にし、睡眠を妨げます。就寝前の飲食は控えて、眠りやすい状態を整えてみてください。体内時計の乱れも睡眠に悪影響を及ぼすため、朝日を浴びて体内時計をリセットし、夜はリラックスモードに切り替えて質の良い眠りをサポートすることが重要です。

日々の習慣を見直すことで、睡眠の質は大きく改善できます。ここでは、睡眠の質を高める16の方法を、厳選して紹介します。どれも手軽に実践できる内容ばかりのため、できるものから生活に取り入れてみてください。
就寝前に白湯やノンカフェインのハーブティーを飲むことで、体と心をリラックスさせ、スムーズな入眠を促します。睡眠の質を高める方法の効果をより高めるには、ストレスの軽減が重要です。カモミールティーやルイボスティーには、鎮静作用や抗酸化作用があり、安眠を助けるとされています。
逆に、冷たい飲み物は体を冷やして覚醒状態に近づけるため、就寝前は避けるのが賢明です。ゆっくりと湯気を感じながら飲む時間を持つことも、心の切り替えスイッチになります。入眠前には、暖かい飲み物で体の中から眠りやすい状態を作ってみてください。
寝る前の食事は、消化器官が活発になり、深い眠りの妨げになります。脂っこいものや高カロリーの食事は消化に時間がかかり、入眠後のノンレム睡眠の質を下げる原因になります。そのため、理想は就寝の3時間前までに食事を終えることです。
どうしても空腹感が気になる場合は、安眠の妨げにならないように消化に優しいヨーグルトやバナナなどを少量食べてみてください。腸内環境も睡眠に関係しているため、食事のタイミングと内容の見直しも重要です。睡眠の質を高める方法として、就寝の3時間前には食事を終えることを意識してみてください。

日中の適度な運動は、交感神経と副交感神経の切り替えをスムーズにし、夜の入眠をサポートするためおすすめです。ウォーキングや軽いジョギングといった有酸素運動は、脳内のセロトニン分泌を促します。また、夜間のメラトニン生成を活性化させる効果があります。
運動のタイミングは日中でも問題ありませんが、就寝する3時間前もおすすめです。ただし、激しすぎる運動は、逆に睡眠を妨げる恐れがあるため、適度な強度で体を動かすことが重要です。日中の活動量を意識して運動することで、自然な眠気を感じやすくなります。軽い運動で体に適度な負荷を与えて、睡眠の質を高めることを意識してみてください。
就寝の1〜2時間前にぬるめの湯船につかることで、深部体温が一時的に上昇し、その後の体温低下がスムーズな入眠につながります。ぬるま湯ではなく熱めのお湯が好きな方は、さらに早めの時間に入浴することで、スムーズな入眠が可能です。
シャワーだけで済ませるのではなく、しっかりと入浴することで副交感神経が優位となり、リラックス状態を作り出せます。そのため、浴槽につかって体を温めることが重要です。また、アロマオイルやバスソルトを取り入れることで、香りによる快眠効果も得られます。
入眠の1〜2時間前の入浴を毎日の習慣にして、スムーズに入眠できる状態を作ってみてください。
コーヒーや緑茶に含まれるカフェインは覚醒作用があり、摂取後4〜6時間ほど体内に残ります。そのため、寝る直前のカフェイン摂取は、入眠の妨げになるため避けた方が賢明です。また、たばこに含まれるニコチンも交感神経を刺激するため、安眠を阻害します。
さらに、一見眠気を誘うように思えるアルコールも、夜中に目覚めやすくなる「中途覚醒」の原因になります。寝酒として就寝前にお酒を飲む方もいますが、睡眠の質を下げ熟睡感を得にくくなるため、あまりおすすめできません。快眠のためには、これらの嗜好品の摂取時間を見直すことが不可欠です。

スマートフォンやタブレットの画面から発せられるブルーライトは、脳を刺激し、メラトニンの分泌を妨げる作用があります。就寝の1時間前には画面を見るのを控え、できれば読書や軽いストレッチなどのデジタルデトックスの時間を設けてみてください。
画面をどうしても見る必要がある場合は、ナイトモードやブルーライトカット機能を活用するのも一案です。就寝前に寝室の電気を消してスマホを見る方も少なくありません。暗い環境でのスマホの使用は、安眠の妨げだけではなく視力の低下にもつながるため、控えた方が賢明です。
室温・湿度・光・音・寝具の5つの要素は、睡眠の質に大きく影響します。そのため、5つの要素を調整して睡眠環境を整えることが、睡眠の質を高めるためには重要です。
室温は16〜20℃、湿度は50〜60%が理想とされています。エアコンや加湿器で調整すると温度と湿度を理想に近づけられます。屋外の光などが気になる場合は、遮光カーテンで外光を遮ってみてください。メラトニン分泌に役立ちます。
寝具は、通気性・保温性・体圧分散性の高いマットレスや枕を選ぶことが重要です。自分に合った睡眠環境を整えることで、自然と深い眠りにつながります。
朝日を浴びることで、体内時計がリセットされ、自然な眠気が夜に訪れやすくなります。体内時計は、1日の周期が24時間より若干長いため、毎日調整しなければいけません。その調整のために欠かせないのが、朝日です。
朝日は脳内でセロトニンを活性化させ、メラトニンの分泌を抑える準備にもなります。起床後30分以内にカーテンを開け、窓際で過ごす習慣をつけてみてください。体内時計をリセットすることで、体内のリズムが整い、睡眠の質を高めることにつながります。

朝食をとることは、体内リズムを整えるために重要です。食事の刺激が消化器系を目覚めさせ、体全体の代謝が活性化します。糖質とタンパク質をバランスよく含む朝食は、セロトニンの材料となるトリプトファンの吸収を助けます。結果として夜のメラトニン分泌にもつながるため、朝食はしっかり摂らなければいけません。
忙しい朝でも、スムージーやヨーグルトなど、簡単なもので構いません。朝食を食べることで仕事や勉強に集中しやすくなるため、睡眠以外の生活にも良い影響を与えます。
快眠を得るためには、トリプトファンやマグネシウム、ビタミンB6やアミノ酸などの栄養素が不可欠です。トリプトファンは大豆製品や乳製品に、マグネシウムはナッツや海藻類に含まれています。ビタミンB6は、動物性のたんぱく質やバナナなどに多く含まれている栄養素です。
これらを日常的に取り入れることで、睡眠ホルモンであるメラトニンの生成がスムーズになり、眠りやすい体質になります。朝昼晩の食事で睡眠の質を高めるために効果的な栄養素を取り入れて、スムーズかつ安眠できるように意識してみてください。
食事のリズムを整えることも、睡眠の質を高めるためには欠かせません。なぜなら、食事のタイミングが不規則だと体内時計が乱れ、夜間の眠気に影響が出るからです。朝昼晩を決まった時間に食べることで、消化・吸収のリズムが整い、夜の就寝時間にも自然と眠気が訪れるようになります。
夕食は、就寝の3時間前には済ませるのがベストです。生活スタイルに応じて、可能な限り毎日の食事時間を一定に保ってみてください。
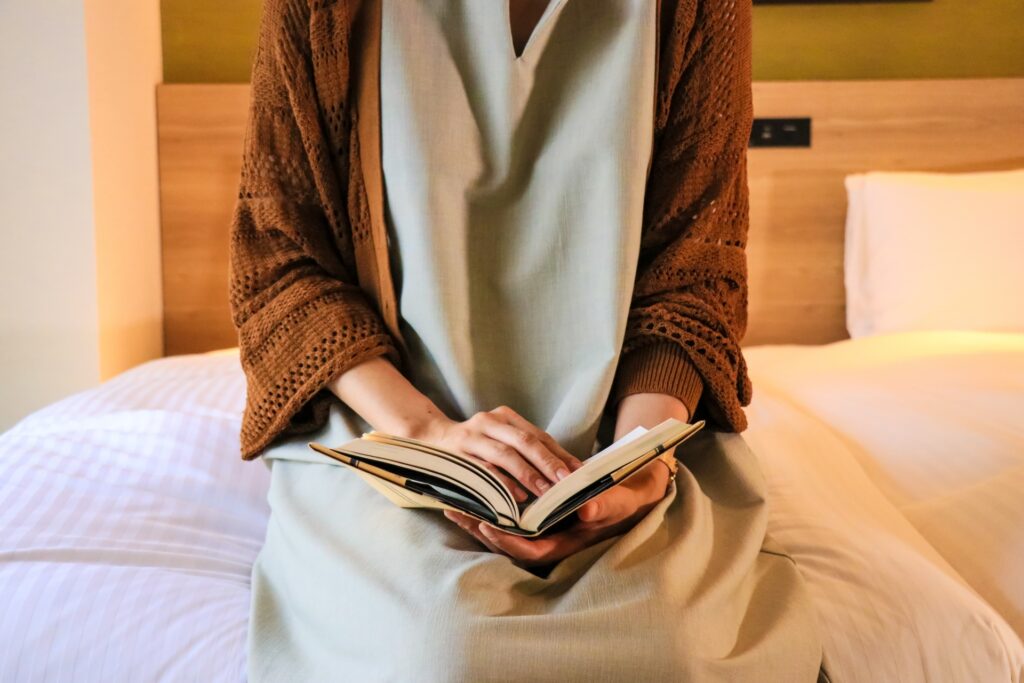
ベッドに入っても眠れないとき、無理に寝ようとするとかえって交感神経が優位になり、睡眠から遠ざかります。そんなときは、一度ベッドを離れて照明を落とした環境で読書や深呼吸をしてみてください。
リラックスすることで、副交感神経が活性化し、メラトニンの自然な生成を促します。暗く静かな環境を保つことがポイントです。ただし、スマホやタブレットなどは脳を刺激するため、使用は避けることをおすすめします。
寝室の温度と湿度は、快適な睡眠に不可欠な要素です。そのため、寝室の温度と湿度の調整も、睡眠の質を高めるためには欠かせません。理想的な室温は夏で25〜27℃、冬で15〜18℃、湿度は1年を通して50〜60%が目安とされています。
エアコンや加湿器、除湿機などを活用し、季節に応じて温度と湿度の調整を意識してみてください。また、寝具の通気性や吸湿性も快適さに直結するため、布団やまくらの素材選びにも注意が必要です。
外の騒音や生活音は、浅い眠りを引き起こす原因になります。そのため、寝室や屋外の音をコントロールすることも重要です。耳栓やホワイトノイズマシンなどを活用することで、不快な音をシャットアウトし、安心感のある環境を作れます。
また、室内で発生する冷蔵庫や空気清浄機の音が気になる場合は、就寝時だけタイマー機能で止めるのも1つの手段です。静寂は、深い眠りを支える鍵になります。自分に適した音の環境を整えてみてください。

就寝前の軽いストレッチは、副交感神経を優位にし、体の緊張をほぐします。肩・首・背中・腰回りをゆったりと伸ばすことで血流が改善され、リラックスした状態で眠りにつくことが可能です。
また、腹式呼吸を繰り返すと副交感神経が優位になり、体がリラックスした状態になります。5〜10分ほどを目安に、腹式呼吸を意識しながらストレッチをしてみてください。ヨガやピラティスの要素を取り入れるのもおすすめです。
毎日の起床時間を一定にすることで、体内時計が安定し、自然な入眠・覚醒リズムが整います。就寝時間が遅くなったからと言って、起床時間を遅らせると、結局体内時計は狂ったままです。眠いのを我慢して起床時間をそろえることで、睡眠の質向上につながります。
休日に寝だめする方もいますが、かえって“社会的時差ボケ”を引き起こし、月曜朝のだるさの原因にもつながります。平日でも休日でも起床時間は大きく変えず、規則正しい生活リズムは、質の高い睡眠への第一歩です。

布団に入っても眠れない経験は、誰にでもあることです。無理に寝ようとすると焦りや不安が強まるうえ、交感神経が優位になって眠れなくなる悪循環に陥ります。この悪循環に陥ると、睡眠時間は悪くなり、寝起きの気分も優れません。
そんなときは、一度ベッドから離れ、間接照明の下で静かに過ごしてみてください。以下のような方法でリラックスしてみてください。
五感を整える習慣を取り入れることで、副交感神経が優位になり自然な眠気が訪れやすくなります。眠気が戻ってきたら、再び横になることでスムーズに入眠できることが多いため、無理に寝ようとせずリラックスしてみてください。

ここまでの解説で睡眠の必要性はわかりました。しかし、睡眠の質が下がると具体的にはどのような影響がでるのか疑問に思う方は少なくありません。睡眠の質が下がると、次のようなマイナスの影響が出ます。
ここからは、それぞれの影響を詳しく解説します。
睡眠不足が続くと、感情のコントロールが難しくなり、不安感やイライラが強くなりやすくなります。これは、脳内のセロトニンやドーパミンのバランスが乱れ、精神的な安定を保つ機能が低下するためです。
睡眠不足は、うつ病や不安障害など、メンタルヘルスのリスクにもつながります。心の不調を感じたら、睡眠をはじめとした生活習慣を見直してみることが大切です。健康的な生活をこころがけることで、自然と精神を整えられます。
睡眠の質が低下すると、ホルモンバランスや自律神経が乱れ、血糖値や血圧の調整がうまくいかなくなります。自律神経の乱れや血圧の調整不良が慢性的に続くと、糖尿病や高血圧、脂質異常症などの生活習慣病のリスクが高まり、大きく健康を損ないかねません。
また、食欲を抑えるホルモンのレプチンが減少し、逆に食欲を増進するグレリンが増え肥満の原因にもなります。生活習慣病は重大な疾患につながる恐れがあるため、睡眠を通して体調を整えることが大切です。
睡眠不足は脳の働きを鈍らせ、集中力・判断力・記憶力・意欲の低下を引き起こします。これは、脳が十分に休息をとれていないために起こる現象で、日中の仕事や学習において致命的なパフォーマンス低下につながります。
交通事故やヒューマンエラーも起こりやすくなるため、社会生活への影響も見逃せません。睡眠が十分にとれていれば、仕事や勉強、運転で普段通りのパフォーマンスを発揮できます。毎日の仕事や勉強に集中するためにも、睡眠の質を高めることが重要です。
睡眠の質が低下すると、目の下にクマができたり肌がくすんだりと、見た目の印象にも大きな影響を与えます。肌のターンオーバーは夜間の深い睡眠中に促進されるため、睡眠が浅いとそのサイクルが乱れ、肌荒れや老化の原因となります。
慢性的な寝不足は「老け顔」の一因となるため、美容を気にする人こそ睡眠の質を重視すべきです。目の下のクマが気になったら、クマの専門クリニックであるKumaCLIに相談してみてください。クマの状態にあった適切な方法で、悩みを解決します。
以下の記事では、クマの種類を解説しているので、併せてご覧ください。

今回は、睡眠の質を高める方法を解説しました。睡眠の質を高めることは単に「よく眠れるようになる」だけではありません。心と体の健康、美容や日中のパフォーマンスにも密接に関わっています。そのため、睡眠の質の低下は、人生に大きな悪影響を及ぼします。
本記事で紹介した16の方法は、どれもすぐに始められる実践的なアプローチばかりです。まずは。「スマホを見ない」「寝る前にストレッチをする」といった簡単な習慣から始めてみてください。
睡眠の質を高めるために重要なのは、リラックスすることと安定的な生活、睡眠環境です。眠れない夜を減らし、朝を気持ちよく迎えるために、今日から少しずつできることから整えてみてください。
睡眠が原因のクマで悩んでいる方は、ぜひKuma CLIへご相談ください。